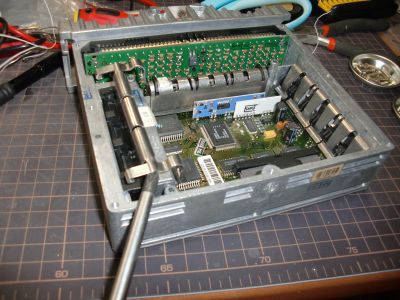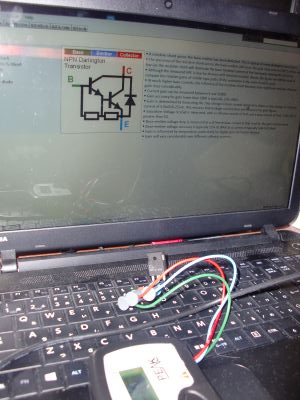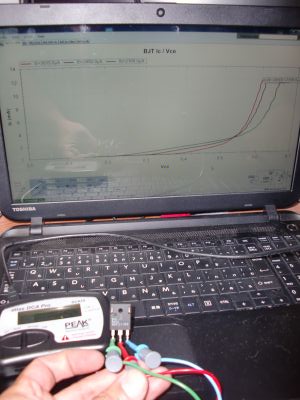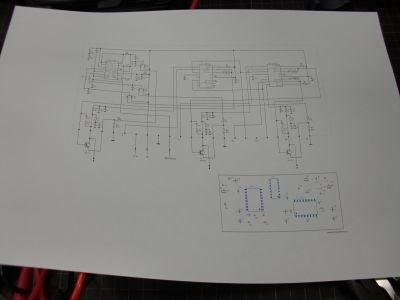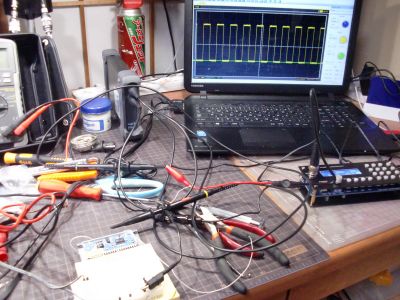2016年7月
ある日突然、エンジンが異常振動するようになりました。
前に一度同じことがあり、その時はイグニッションコイルを交換して治りました。
ところが、イグニッションコイルを調べても異常がありません。
これは、いよいよエンジンコンピューターが逝ってしまった様です。
買ったら高いし、修理に挑戦することにしました。
まず、エンジンコンピューターを取り出します。

バッテリーをおろし、後ろの樹脂製カバーを外します。

現れたABSコンピューターのでかいコネクタを外します。
コネクタの下の金属のバネを押し下げると、左側が
持ち上がり、外れます。

10mmのナットを2つ外し、ABSコンピューターを外します。

ABSコンピューターを固定していた台座金具をビス2本外し
取り外します。

エンジンコンピューターの2つの大きなコネクタを外します。
コネクタの上の金具を起こすと外れます。

写真がぼけてしまいました。10mmのボルトを2本外すと、
エンジンコンピューターを取り出すことが出来ます。

外したエンジンコンピューター。 |
家に持ち帰り、蓋を開けます。
T10のトルクスボルトで固定されています。
とても固く締まっていて、トルクスビットに小さなモンキー
レンチをかけて緩めました。
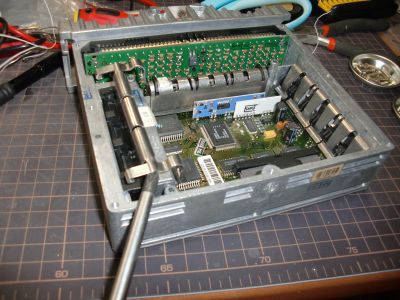
故障箇所は、ネットで調べて大体見当をつけています。
多分、イグナイター基板のどこかか、終段のトランジスタ
が飛んでいると思われます。
終段トランジスタを放熱板(金属ケース)に押し付けている
金具を外します。端のツメを小さなマイナスドライバーで
起こして外し、きつくはまっている金属を大きなプラス
ドライバーで少しずつこじって抜き取ります。 |

裏蓋も同様に外します。 |

イグナイター基板を取り外します。
22個のハンダ付けを、熱しながらバキュームで取り去り、
出来る限り、端子をフリーにします。
アース線のハンダを取り除くのはちょっと難しかったので
すが、数個でしたので、これは溶かしながらイグナイター
基板を抜くことにしました。 |

無事外れました。 |

同様に、終段トランジスタを3つとも外します。
M104エンジンには、イグニッションコイルが3つしか
ありません。6気筒なのに3つしかないのは、2気筒を同時
に点火しているためです。
6気筒エンジンは設計上、2つのシリンダが常に同じ位置に
いて、片方が上死点で点火するとき、もう片方は燃焼済ガス
の排気を行って、吸気を始める状態にあります。
そのときに点火しても何も問題ない(何も起こらない)ので、
2つのシリンダを同時に点火するようにして、点火機構を
簡略化しているのです。 |
まずは終段トランジスタのチェックです。
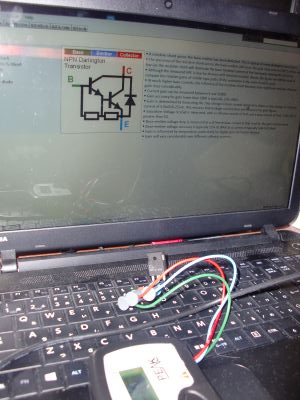
半導体チェッカーでチェックします。
ネットで仕入れたBUX127チップのデータシート
通り、ちゃんとダーリントン素子として認識
されました。
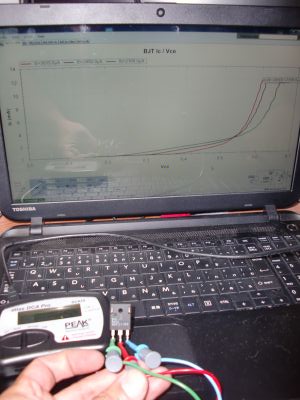
特性もチェックします。
結果、3つとも異常はないようです。 |
すると、いよいよイグナイター基板が壊れているようです。
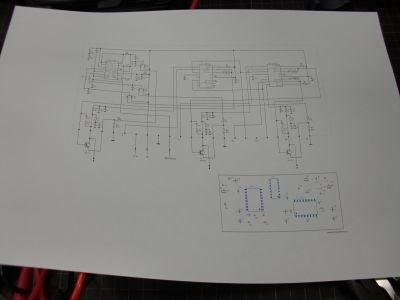
まず、ネットでイグナイター基板の回路図を見つけて
来ました。
なんとロシアの掲示板に貼られていました。
ロシアの人は、部品が入手しにくいのか、ちゃんと修理
するのですね。 |
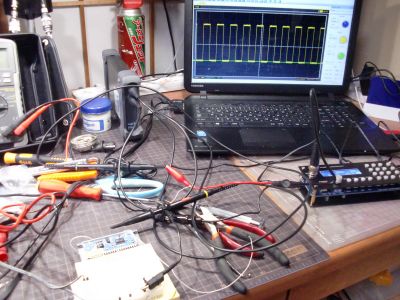
ファンクションジェネレータで擬似信号を回路に投入して、
各ポイントの波形をオシロスコープでチェックします。
回路は、イグニッションコイルに電気を流す部分と、それを
検知してコンピューターにフィードバックする部分に分かれて
います。
点火異常をここで検知して、ミスファイヤーをカウントしたり、
触媒マフラーを守るために燃料カットとかするのでしょうね。 |

異常検知の部分は問題ありませんでした。
3つの点火系のうち、一つの回路のある部分の抵抗が焼き
切れている様です。
この基板は、薄いセラミックで作られていて、抵抗器は
パターンに印刷されている様で、付け替えることが出来
ません。
仕方がないので、ICの上から立体配線です・・・(^^;。 |

終段トランジスタも元に戻しました。 |

イグナイター基板も戻しました。 |

放熱板に終段トランジスタを押し付ける金具も戻し・・・ |

完成です!
雨が入らないように、ケースをしっかりと閉めて・・・ |

上部コネクタの、イグニッションコイルに行く部分の抵抗値
を測ります。
3回路ともこれぐらいの数値だったらOKです。 |
サクッと車に取り付け、恐る恐るエンジン始動!
異常振動はなくなり、完璧です。
なんと、エンジンコンピューターが部品代10円もかからなくて治りました。
ただし、壊れた箇所によって対処は異なりますし、技術的にもちょっと高度かもしれませんので、
万人にお勧めできる修理ではありません。
でも、だんだん部品が手に入らなくなりますし、中古ではすでに壊れているかもしれません。
ロシアの方々のように、交換でなく、頑張って修理しながら乗らなければならなくなって来ますよね。
もし、参考にされて挑戦されるかたはご自身の責任でお願いしますね。